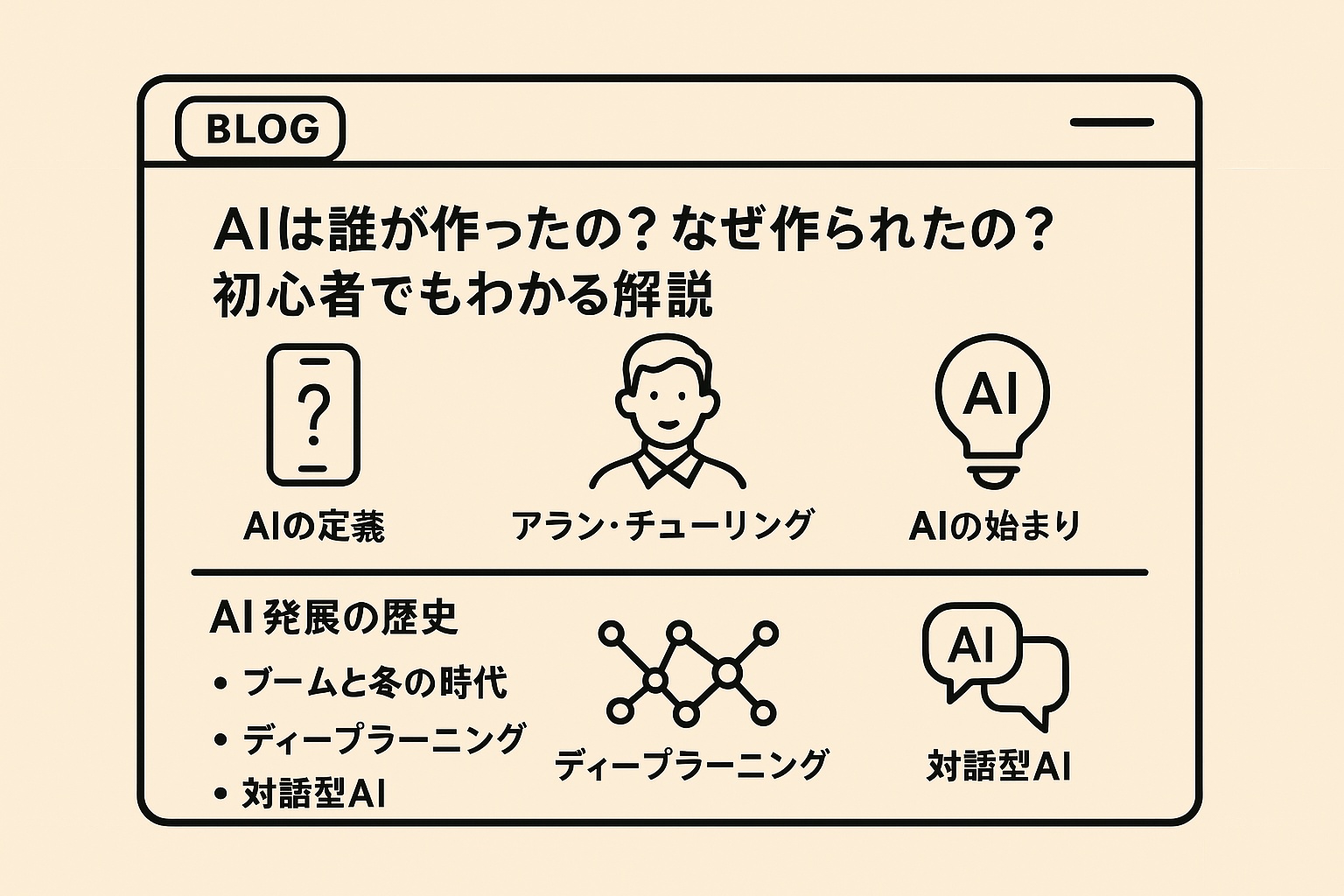そもそもAIって何?意外と知らない基本
気づけば身近、AIはこんなところに
いつのまにか、AIはわたしたちの生活に入りこんでいます。
気づかないうちに、いろんな場面で当たり前のように使われています。
たとえば、こんなところです。
これ、どれもAIが裏で働いてくれてるからなんです。
便利すぎてスルーしがちですが、すでに日常にとけこんでいます。
「AIって何?」と聞かれて困る理由
これは友人が言っていたのですが、これを聞いてまともな答えが返ってきたことないみたいに言っていました。
すごそうな感じはあるけど、正体はよく知らない。
けっこういると思います。
この記事でわかる3つのこと
本記事ではこのあと、こんなことを紹介します。
- AIはどうして作られたのか
- 誰が最初に作ったのか
- どんなふうに進化してきたのか
分かりやすく紹介していきます
AIを作ったのは誰?どうして誕生したの?
最初のひらめきはアラン・チューリングから
AIのルーツは、今から70年以上前にさかのぼります。
当時、「人間みたいに考える機械って作れるのかな?」と考えた人物がいました。
イギリスの数学者、アラン・チューリングです。
チューリングが出したアイデアはこちらです。
人間と機械が会話して、どちらかわからないほど自然なら、それは“考えている”と言えるのでは?
この考え方が、のちに「チューリングテスト」と呼ばれるようになります。
これがAIの出発点とされているんですね。
チューリングはプログラムを書いたわけではありません。
でも「考える機械」という考えそのものが、ここから動き出したわけです。
「人工知能」という言葉をつくったのは?
チューリングのあと、今度はアメリカで動きが出てきます。
「機械の知能をもっと本格的に研究しよう」という流れが強まりました。
その中心にいたのが、ジョン・マッカーシーという研究者です。
彼は1956年に「ダートマス会議」という研究会を開きました。
その場で、初めて「Artificial Intelligence(人工知能)」という言葉を使います。
ここが、AIという分野が正式にスタートしたタイミングとされています。
マッカーシーは、言葉を作っただけではありません。
AI専用のプログラミング言語「LISP」も開発しました。
つまり、
という感じで、AIの基礎を整えていった人物です。
AIはなぜ作られたのか?原点はここ
最初の動機はとてもシンプルでした。
「人の頭の中って、どう動いてるんだろう?」という疑問から始まったんです。
こんな問いがベースにありました。
当時はまだ夢のような話だったかもしれません。
でも、その不思議さやワクワク感が、AIを研究する原動力になっていきました。
やがてAIは、
という方向に広がっていきます。
もともとは研究のために始まったものですが、
少しずつ医療や仕事のサポートにも応用されるようになりました。
ブームと進化でたどる、AIの成長ヒストリー
何度も訪れた「AIの冬」とは?
AIは、順調に育ってきたわけではありません。
実は、ブームがきては止まり、また盛り上がる……という波をくり返してきました。
最初のブームは1950年代後半から。
当時のAIは、ルールをあらかじめ人が決めておき、それに従って判断させるスタイルでした。
でも現実の問題はもっと複雑でした。
うまくいかないことが増えて、「これってあまり使えないかも?」という空気に。
ここで、最初の「AIの冬(停滞期)」に入ります。
1980年代の復活、でも続かなかった理由
次に注目されたのが「エキスパートシステム」という考え方です。
1980年代に登場しました。
これは、専門家の知識をコンピューターに入れて、問題を解決させる仕組みです。
特定の分野ではちゃんと成果が出ていました。
ただ、こんな課題もありました。
結局、コストや手間の問題で広く使うのはむずかしくなってしまいます。
ここで2回目の「AIの冬」が訪れます。
ディープラーニングでAIが一気に進化
状況が大きく変わったのは2010年代です。
コンピューターの性能が上がり、データも大量に使えるようになりました。
そこで登場したのが「ディープラーニング」です。
AIが自分でパターンを見つけながら学ぶ方法です。
有名な話があります。
Googleが大量の猫画像をAIに見せたところ、何も教えていないのに「これが猫っぽい」と気づいたそうです。
この時期から、AIは以下のようなことが得意になります。
現実世界で、いろんな場面にAIが入りこみはじめました。
ChatGPT登場で会話するAIの時代に
さらに進化したのが、2020年代です。
会話ができるAIが登場します。
2022年には「ChatGPT」が公開されました。
まるで人と話しているような自然なやりとりができるようになります。
このAIは「大規模言語モデル」と呼ばれています。
できることはたとえば、
これが「第4次AIブーム」と呼ばれている時代です。
今では、ビジネス・教育・クリエイティブなど、いろんな場所で使われています。
ざっくりわかるAIの歴史年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1950年 | アラン・チューリングが「チューリングテスト」を提案。「機械は思考できるか?」を考えるきっかけに。 |
| 1956年 | ジョン・マッカーシーが「人工知能(AI)」という言葉を初めて使用。 ダートマス会議が開催され、AI研究が正式に始まる。 |
| 1960〜1970年代 | ルールベースのAI(エキスパートシステム)登場。 例:「ELIZA(1966年)」=簡易的な会話プログラム。 |
| 1980年代 | 日本の「第五世代コンピュータ」など、世界的にAIブーム。 しかし期待が大きすぎて、研究資金が打ち切られ「AIの冬」に。 |
| 1997年 | IBMの「ディープ・ブルー」がチェス世界チャンピオンのカスパロフに勝利。AIが初めて人間の頂点を破る。 |
| 2006年 | ジェフリー・ヒントンが「ディープラーニング(深層学習)」のブレイクスルーを発表。 AIの第二の黄金時代が始まる。 |
| 2012年 | 「ImageNet」コンテストでディープラーニングが画像認識の精度で圧勝。AI研究が爆発的に加速。 |
| 2016年 | Google DeepMindの「AlphaGo」が囲碁の世界トップ、イ・セドルを破る。 人間では勝てない領域へ到達。 |
| 2022年 | OpenAIの「ChatGPT」が公開。自然な対話能力で世界に衝撃を与える。 AIの一般普及が本格化。 |
| 2023年以降 | GPT-4などの大規模言語モデルが登場。AIが教育・医療・創作・仕事に急速に応用され始める。 |
これからのAIと、どう向き合う?
AIは人の知能をヒントにしたツール
ここまで見てきたように、AIの始まりは研究者たちの好奇心からでした。
「人の考え方をまねできるかも?」という発想が、出発点になっています。
チューリングやマッカーシーたちは、
- 人の思考を参考にしながら
- 新しい知能のかたちを
- じっくり探っていたわけです
そのAIが、今では研究室を飛び出して、社会の中にどんどん広がっています。
最初は実験のような存在でしたが、少しずつ使えるツールへと育ってきました。
時間をかけてじわじわ育った、そんな道のりです。
使いこなす時代へ、一緒に進むAIとの関係
AIがここまで進んできた今、大事になってくるのは「どう使うか」です。
ぜんぶ任せるというより、人の力と組み合わせて活かすことがポイントになります。
たとえば、こんな使い方があります。
「AIに使われる」のではなく、
「一緒に進んでいく相棒」のような存在として付き合っていく。
そんな距離感が、ちょうどいいのかもしれません。
まとめ|止まらないAIの進化、ChatGPTはどこまで行く?
AIの歴史は、ひとつのひらめきから始まり、ブームと停滞をくり返しながら、少しずつ現実に近づいてきました。
そして今、AIの進化スピードには、全人類びっくりしているような状態ではないでしょうか。
もう、止まることはなさそうです。これから先、どこまで進んでいくのか、とても気になるところです。
そんななか、2025年3月25日、OpenAIがChatGPTの画像生成機能の大幅アップデートを発表しました。
圧倒的に出来ることの幅が広がりました。しかもどれもハイクオリテイにこなしてくれます。
以下の記事にて一通りの紹介をしておりますので、参考にしていただけたら嬉しいです。